
安永2年(1773)、7代藩主 亀井矩貞が、城下繁栄を祈って京都の伏見稲荷を勧請したのが始まり。参道には奉納された約1000本もの鳥居が、ふもとから山腹の境内まで隙間なく続いている。
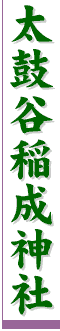


背景の緑に朱色が映える。


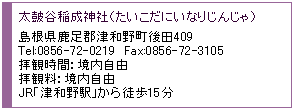






2002年に新調されたばかりである。





残念ながら、今は穴の入り口は塞がれ、丸く開けられた小さな窓から、なかを覗うのがやっとであった。三浦さんがせめても?と油揚げをお供えしてくれた。


| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|||||||||||||||||
 |
|
|
||||||||||||||||
| |
太皷谷稲成神社は日本5大稲荷の1つ。 安永2年(1773)、7代藩主 亀井矩貞が、城下繁栄を祈って京都の伏見稲荷を勧請したのが始まり。参道には奉納された約1000本もの鳥居が、ふもとから山腹の境内まで隙間なく続いている。 |
|
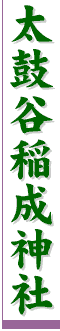 |
|
||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
 |
 |
|
||||||||||||||||
| 太鼓谷稲成神社
拝殿。 背景の緑に朱色が映える。 |
|
|||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
| この鳥居のトンネルを登りきったところが拝殿である。神社様式の典型を思わせる大屋根、鮮やかな朱色に大しめ縄が目を引く。この境内から津和野の町が一望できると教えてもらったが、朝からの雨で、下界は雲のなかに沈んでいた。 | |
|||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
| |
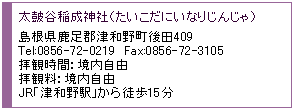 |
|
|
|||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
| |
 |
|
||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||
 |
 |
 |
|
|||||||||||||||
 |
拝殿に飾られた巨大なしめ縄。 2002年に新調されたばかりである。 |
 |
|
|||||||||||||||
| 参道下のお店や境内では狐の好物である油揚げが、ろうそくと一緒に売ってる。 | |
|||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
| |
 |
 |
|
|||||||||||||||
| |
全国各地にある稲荷神社のなかでも、「稲成」と書くのはこの太鼓谷稲成だけらしい。大願成就、どんな願いでも叶えてくれるという、大変なご利益があるといわれているためで、家内安全、学業促進、商売繁盛に開運厄除と、様々な願いの参拝客があとを絶たない。 | |
|
|||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||
| |
 |
|
|
|||||||||||||||
| |
参道を上がって右側の奥に、小さな祠があった。ちょうど狐が隠れていそうな大きさの洞穴で、通称「キツネのトンネル」。この穴が、実は京都の伏見稲荷につながっているという言い伝えが残る。 残念ながら、今は穴の入り口は塞がれ、丸く開けられた小さな窓から、なかを覗うのがやっとであった。三浦さんがせめても?と油揚げをお供えしてくれた。 |
|
|
|||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||
| 参道横の祠には不思議な言い伝えが今も残る。 | |
|||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||
| ▲ページトップに戻る | ||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||