







ここで福島さんから築城に関わる興味深い話を聞きました。この堅牢な石垣を作るため、京都から優秀な石工を呼び寄せたのだそうです。その石工のもとで地元の職人たちが、盛岡産の花崗岩を用い、東北三城跡といわれるこの城壁を組み上げました。今は、春の桜、夏の緑、秋の紅葉、冬の雪と、四季を通して美しい公園として、盛岡市民の憩いの場になっています。・・・盛岡で出会ったひとつの京都です。
| 盛岡市岩手公園 / 入園料:無料 盛岡市内丸1-6 |
 |
||||
 |
||||
| | 岩手公園(盛岡城跡)を散策 | 中の橋から上の橋界隈を歩く | | ||||
 |
||||
 |
||||
 |
||||
 |
 |
|||
| 岩手公園(盛岡城跡)を散策 |  |
|||
|
盛岡ふるさとガイドの福島さんに、岩手公園を案内してもらいました。
盛岡城は慶長年間に南部信直が築城し寛永10年(1633)に完成します。しかし、明治維新に南部藩は、佐幕派として官軍と戦い、秋田戦争に敗れ無条件降伏をし、天守閣は明治7年(1874)に取り壊されます。今は堅牢な石垣のみが残っていて、当時の姿をもう見ることはできません。 ここで福島さんから築城に関わる興味深い話を聞きました。この堅牢な石垣を作るため、京都から優秀な石工を呼び寄せたのだそうです。その石工のもとで地元の職人たちが、盛岡産の花崗岩を用い、東北三城跡といわれるこの城壁を組み上げました。今は、春の桜、夏の緑、秋の紅葉、冬の雪と、四季を通して美しい公園として、盛岡市民の憩いの場になっています。・・・盛岡で出会ったひとつの京都です。 |
||||
|
||||
 |
この公園の中にはいくつかの記念碑が立っています。石川啄木の「不来方(こずかた)のお城の草に寝ころびて空に吸われし十五の心」の歌碑は、この公園の二の丸跡にあります。少年時代の啄木が学校から抜け出し、ここで文学書や哲学書を読んでいたそうです。今はここからは岩手山を見ることはできませんが、この場所を好んだ啄木は、どのような景色を見ていたのだろうと思います。また、公園内には、青春時代を盛岡で過ごした、もうひとりの天才、宮沢賢治の詩碑もあります。
|
|||||||
 |
啄木碑 |
|||||||
|
盛岡の先人には、大正7年に平民として初めて首相になった原敬(1856〜1921)。国語辞典の執筆・監修で知られる金田一京助(1882〜1971)。太平洋戦争の終結に尽力した海軍大将、米内光政。そしてこの碑の人物、五千円札の肖像で知られる新渡戸稲造です。東大の入学式の面接で「願わくはわれ太平洋の橋とならん」と答え、その名言にふさわしい国際人となりました。大正9年には国際連盟の事務次官に就任。自らは、アメリカ人と国際結婚をしています。盛岡には、こうした先人たちゆかりの地や、記念碑、美術館、博物館があり、ゆっくりと街を歩きながら歴史を楽しめます。
|
||||||||
| 県立図書館の近くにある原敬(はらたかし、通称はらけい)の碑には戊辰戦争以来の盛岡の情勢を現す文章が刻まれています。「朝廷に弓をひいたのではない、ただの意見の相違である」といった意味の言葉は、近代盛岡の実情をよく表していると思います。 原敬は、藩校作人館(仁王小学校の前身)で学び上京、新聞記者などを経て大正7年(1918)に首相となります。歴代の士族出身の首相に代わる、日本初の平民宰相として国民に歓迎されました。日本における政党政治の第一歩を記した人物としても知られています。しかし、原敬はその開明性のために極右勢力に狙われ、大正10年(1921)11月、東京駅で凶刃に倒れます。 | ||||||||
新渡戸稲造記念碑 |
 |
|||||||
原敬の碑 |
||||||||
|
 |
|||||||
|
南部中尉銅像台座
|
||||||||
|
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
|
慶長年間に、上の橋から中の橋の中津川東岸のこの通りには、紙町、鍛冶町、紺屋町という一続きの大きな街並みがつくられていました。そして幕末には屈指の豪商老舗が軒をつらね、盛岡城下の主要な商店街となっていました。この豪商の中には、京都・滋賀の出身者も多く、中でも「近江商人」は盛岡の商業発展の中心的な役割を果たしています。
|
||||||||||||||
茣蓙九店内 |
||||||||||||||
 |
京都の産物が商人の手によってこの地に届けられ、新たな盛岡の文化として発展した歴史を、今はっきりと知ることはできませんが、当時の人々にとって「京都」はどのようなところだったのだろうと思ってしまいます。話は離れますが、郊外の岩手山麓に、明治24年創業の小岩井農場があります。「小岩井」の名は、小野氏、岩崎氏、井上氏の頭文字からつけられたものですが、この小野氏こそ、京都・盛岡を拠点に活躍した財閥小野組です。後に財閥としては姿を消しますが、京都との深い関わりの足跡がこの地に残っています。
|
 |
||||||||||||
|
紫紺染めの店
|
||||||||||||||
大正年間の 木造洋風事務所建築の 典型といわれる番屋 |
||||||||||||||
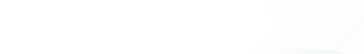 |
 |
||||||||
|
|||||||||
| ▲このPAGEトップへ | |||||||||
 |
|||||||||